届出・証明
本人確認についてのご案内
〇住民票・戸籍謄抄本などの交付請求時に本人確認書類の提示が必要となります。また、委任状が必要な場合がありますのでご注意ください。市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
平成20年5月1日から、住民基本台帳法及び戸籍法の一部改正の施行により住民票の写し等や、戸籍の謄抄本等の交付、また、各種住所異動・戸籍届出時に本人確認が義務づけられています。
これは、個人情報や証明書等を自分の知らないところで他人が不正に取得することのないよう、あるいは、虚偽の届出をすることにより真実でない記載等をされることのないようにするためのものです。
【本人確認書類の例】
1.官公署が発行した顔写真付きの証明書
(例:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カード、運転経歴証明書、本人の写真が貼付された各種免許証・許可証・資格証等)
2.官公署が発行する書類等
(例:健康保険の被保険者証、各種医療証や年金証書等)
3.その他、本人であることを確認することができる市長が適当と認める書類
注:有効期間のあるものについては、有効期間内のものです。
〇正当な請求事由の明示が必要となります。
<本人または同居の親族の場合>
請求書に、請求事由の記入をお願いすることになります。
(これは、強制ではありませんが、なりすまし等による虚偽の請求を防ぎ、皆様個人の情報を守るためご協力をお願いします。)
<上記以外の方の場合>
請求書に、正当な請求事由を詳しく書くことが必要です。
(自己の権利を行使したり、自己の義務を履行するために住民票の写し等や戸籍の記載事項を確認したりする必要がある場合や、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合など)
〇住民票の写し等の請求時に、本人及び同居の家族の方以外は、原則 「委任状」 が必要となります。
〇戸籍の請求時に、戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系親族の方以外は 「委任状」が必要となります。
〇郵送で請求の場合も本人確認が必要です。
窓口での本人確認の方法に準ずる写しの同封が必要です。(送付先は写しで確認できる現住所になります。)
〇罰則が強化されました。
個人情報保護の観点から、不正手段により住民票の写し等や戸籍の謄抄本等の交付をうけたものに対する罰則規定が強化されました。
戸籍届出
| 届出の 種類 |
届出期間 | 届出人 | 届出地 | 届出に必要なもの |
|---|---|---|---|---|
| 出生届 |
子の出生の日から出生の日を含めて14日以内
注:届出の期日(14日目)が市役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日 |
子の父または母 注:父または母の届出が不可能な場合は同居者、出産立会人(医師、助産師又はその他の者)の順 |
|
注:出産された病院等の医師等が記入(証明)するものです。多くの場合、出生証明書部分を記入(証明)済みの出生届書が病院等から交付されます。
|
| 死亡届 |
届出人が死亡の事実を知った日から事実を知った日を含め7日以内
注:届出の期日(7日目)が市役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日 注:国外で亡くなった場合は3か月以内 |
【届出義務者】 次の順序によって届出をしなければなりません。先順位者がある場合でも後順位者が届出をすることができます。 1.同居の親族 2.その他の同居者 3.家主、地主、家屋管理人又は土地管理人
【届出資格者】 届出義務はないが、届出をすることが認められています。
|
|
注:死亡届書と一体になっており、死亡診断書は病院、死体検案書は警察から発行されます。
|
| 婚姻届 | 届出した日から法律上の効力が発生するので届出期間は定められていない | 夫になる人および妻になる人 |
|
|
| 離婚届 |
同上 注:裁判離婚の場合は裁判の確定した日から10日以内 |
注:裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。 |
|
|
| 転籍届 | 同上 |
戸籍の筆頭者および配偶者 注:どちらかが除籍されている場合は、在籍されている方の署名のみで届出してください。 |
|
なし |
- 婚姻届、認知届、協議離婚届、養子縁組届及び協議離縁届については、他人による虚偽の届出を防ぐため、運転免許証、パスポート、在留カード、マイナンバーカード(顔写真付き)、運転経歴証明書など本人確認ができる官公署が発行した顔写真付きで有効期間内の書類等によって、届出人の本人確認をしますのでご協力をお願いします。
なお、本人確認の書類等がない場合でも届出書は受理できますが、届出の事実を本人あてに通知します。 - 婚姻や離婚、養子縁組・養子離縁など、氏名・住所・性別・生年月日が変更になる届出をされる方で、桜井市に住民登録のある方は、マイナンバーカードも持参してください。(券面事項を更新します。)
- 入籍届・養子縁組届・養子離縁届・認知届、その他の届出については、詳しくは市民課にお問い合わせください。
- 土日祝日の12時から13時は死亡届の受理ができませんので、あらかじめご了承のほど、お願いいたします。
住民登録
| 届出の種類 | 届出期間 | 持参するもの |
|---|---|---|
| 転入届 | 市内に引越してきた日から14日以内 |
|
| 転出届 | 市外に転出する前か、転出した日から14日以内 |
外国に1年以上移住する場合も同様です。 |
| 転居届 (住所変更届) |
市内で住所変更をした日から14日以内 |
|
| 世帯変更届 | 世帯主が変更になったときまたは世帯の分離・合併があったときから14日以内 |
|
- 住民異動届については、他人による虚偽の届出を防ぐため、住基カード、マイナンバーカード(写真付き)、運転免許証、パスポート、在留カード、運転経歴証明書など本人確認ができる官公署が発行した顔写真付きで有効期間内の書類等によって、届出人の本人確認をしますのでご協力をお願いします。
なお、本人確認の書類等がない場合でも届出できますが、届出の事実を本人あてに通知します。 - 届出書以外に、異動される方の委任状が必要な場合もあります。詳しくは、市民課にお問い合わせください。
外国人登録
外国人登録制度の変更とお知らせ
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法・入管法が変わりました。 外国人の住民の方は、住民基本台帳制度の対象となり、住所の証明が「登録原票記載事項証明書」から「住民票」に変わりました。
- 短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人住民で住所を有する方について住民票を作成します。
- 外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしている複数国籍世帯は、同一世帯であれば世帯ごとに住民票を発行します。
- 出入国在留管理庁での在留期間更新などの手続き後、市役所への届出は不要となります。
- 出入国在留管理庁や市役所への手続きをしていないため、外国人登録証明書等の在留期間が満了している場合などには、住民票が作成されないことがありますので、所定の手続きをしてください。
外国人登録証明書(カード)が、切り替わります。
改正法施行日(平成24年7月9日)後も当分の間、現在の外国人登録証明書は引き続き有効です。(下記参照)
【特別永住者の場合】
外国人登録証明書は、次回確認(切替)申請後、「特別永住者証明書」に切り替えとなります。 なお、有効期間は次回確認(切替)申請期間の初日(誕生日等)までとなります。 (例えば、申請期間が「平成29年4月1日から30日以内」の方であれば、「平成29年4月1日」までが有効となります。) また、次回確認(切替)申請期間が改正法施行日(平成24年7月9日)から3年以内に到来する方については、3年以内(平成27年7月8日まで)に切り替えてください。 手続きについては、今までと同様に外国人登録の窓口にて受付していますので、外国人登録証明書または特別永住者証明書、写真1枚(16歳以上の方:縦4センチメートル×横3センチメートル)、旅券(交付を受けている方)を持参してください。
【永住者の場合】
外国人登録法廃止後、3年以内(平成27年7月8日まで)に出入国在留管理庁にて「在留カード」に切替の交付申請をしてください。
【特別永住者・永住者以外の方の場合】
在留期間満了日までに出入国在留管理庁にて「在留カード」に切り替えの交付申請をしてください。。
詳しくは、出入国在留管理庁へお問い合わせください。住所変更をする際には、在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書のいずれかと、マイナンバーカードまたは通知カードを必ず持参し、市民課窓口で手続きをしてください。転入・転出する時
転出届をして転出証明書の交付をうけた後、転入先の市区町村長に転入届をする必要があります。
国外に転出する場合
再入国許可を得ている場合であっても原則として転出届が必要です。
詳しくは、総務省・法務省ホームぺージをご覧ください。総務省ホームページ
各リンクテキストをクリックすると、新しいウィンドウが開きます
【外国人住民に係る住民基本台帳制度について】
法務省ホームページ
各リンクテキストをクリックすると、新しいウィンドウが開きます
【入管法が変わります】
【特別永住者の皆さんへ】
2012年7月特別永住者の制度が見直されました。
【日本に在留する外国人の皆さんへ】
2012年7月入管法が変わりました。新たな在留管理制度がスタート!
印鑑登録
| 届出人 | 確認事項 | 持参するもの | 登録証の交付 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 本人であることが受付で確認できる場合 | (1)登録しようとする印鑑 (2)本人であることが確認できるもの 次のいずれか1つ
|
申請日(即日交付) |
| 本人であることが受付で確認できない場合 受付後、本人あて照会書を簡易書留にて郵送します。 |
|
回答書(照会書)持参の日に次のものをご持参ください (1)登録しようとする印鑑 (2)自署押印した回答書 (3)本人であることが受付で確認できる下記のいずれかの書類 (4)代理人に依頼する場合は上記(1)~(3)のほかに委任状と代理人の印鑑(認印)及び代理人が本人であることが受付で確認できる下記のいずれかの書類 本人確認書類 (ア)住民基本台帳カード・マイナンバーカード(写真付き)・運転免許証・パスポート・在留カード・運転経歴証明書など官公署で発行する写真貼付(写真に浮出プレス、せん孔による契印があるものに限る。)した書類等で有効期間内のもの (イ)健康保険証、国民健康保険証、各種共済組合等の被保険者証 |
|
| 代理人 | 印鑑登録を代理人に依頼する場合 受付後、本人あて照会書を簡易書留にて郵送します。 |
|
印鑑登録できる人
市内に住んでいる15歳以上で意思能力を有する者で、住民基本台帳に登録している人は、1人1個に限り、印鑑登録できます。
登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名の全部または一部を表していないもの。
- 職業や屋号など氏名以外の事項を表しているもの。
- ゴム印その他の印鑑で印形の変化しやすいもの。
- 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形より小さいもの。または、1辺の長さ25ミリメートルの正方形より大きいもの。
- 印影の不鮮明なもの。
- 流し込み、機械ぼり、その他によって多量に同一のものが製造市販されているもの。
- 同一世帯で登録済みの印鑑とよく似たもの。
- 前各号のほか、市長が不適当と認めるもの。
印鑑登録証
- 印鑑登録証は、あなたが印鑑の登録を受けていることを証明する大切なものです。登録印鑑同様大切に保管して下さい。
- 印鑑登録証をなくしたときは、第三者による不正使用を防止するためすぐに届けてください。やむを得ない理由によりすぐに届けることができない場合は、とりあえず電話等により連絡してください。
- 登録印鑑をなくしたときは、印鑑登録の廃止申請をしてください。
各種証明書の申請
各種証明書等の申請については、市民課の窓口に用意している申請書に記入していただくか、又はホームページの「申請書ダウンロード」にて申請書をプリントアウトの上、先に記入して窓口に持参してください。
ただし、住民票については、本人及び同居の家族以外、戸籍については、戸籍に記載されている方又はその配偶者・直系親族の方以外は委任状が必要です。
なお、申請についての詳しい説明については、「申請書ダウンロード」の説明をご覧いただくか、窓口に直接おたずねください。
主な証明の手数料(1通・1件あたり)
- 戸籍(全部事項証明・個人事項証明・一部事項証明)…450円
- 除籍・改製原戸籍(謄本・抄本)…750円
- 戸籍の附票…300円
- 戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書…400円
注:当該戸籍電子証明書が証明する事項と、同一の事項を証明する戸籍謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を同時に行う場合は無料。
- 除籍電子証明書提供用識別符号等通知書…700円
注:当該除籍電子証明書が証明する事項と、同一の事項を証明する除籍謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を同時に行う場合は無料。
- 住民票(謄本・抄本・記載事項証明)…300円
- 印鑑登録証明書…300円
- 身分証明書(後見の登記及び破産手続等の通知を受けていない証明)…300円
- 独身証明書…300円
- 戸籍記載事項証明書…350円
- 除籍記載事項証明書…450円
- 受理証明書…350円(上質紙は1,400円)
- 届書記載事項証明書…350円
- 届書等情報内容証明書…350円
- 広域交付住民票…300円
- マイナンバーカード再交付…800円(電子証明書を発行希望される場合は200円必要です。)
桜井市本人通知制度の実施について
制度の概要について
この制度は、住民票又は戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して、その事実を通知するものです。 本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。 また、制度の導入により、不正請求が発覚する可能性が高まることから不正請求を抑止する効果が期待されます。
この制度の利用は、希望者に限るため事前に登録が必要です。実施日
平成24年1月4日
本人通知制度の流れ(事前登録から通知までの流れ)
- 事前登録 … 通知を希望する人が事前に市民課で登録します。
↓ - 代理人・第三者からの請求 …市民課で、住民票の写し等の請求があれば審査のうえ交付します。
↓ - 交付事実の通知 …事前登録者に、交付した事実を通知します。
事前登録ができる人
- 桜井市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている人
(住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた人を含む)
- 桜井市の戸籍に記載されている人
(戸籍から除かれた人を含む)
死亡した人、失踪宣告を受けた人、職権消除された人は登録できません。事前登録に必要なもの
桜井市本人通知制度事前登録申込書と
- 窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・マイナンバーカード(写真付き)・在留カード・運転経歴証明書等で有効期間内のもの)
- 代理人(登録される人から委任を受けた人)が来られる場合は、委任状と代理人の本人確認書類
- 法定代理人(未成年者の場合など)が来られる場合は、戸籍謄本などの代理人の資格を証明する書類(桜井市の住民票、戸籍で確認できる場合は資格を証明する書類を省略できます。)と法定代理人の本人確認書類
- 郵送での申込みの場合は、本人確認書類の写し(法定代理人の場合は資格を証明できる書類も必要)
登録の期間
令和7年4月1日より、登録機関は廃止しました。(旧:3年間)
本人通知書の記載事項
- 交付年月日
- 交付証明書の種別
- 交付枚数
- 交付請求者の種別
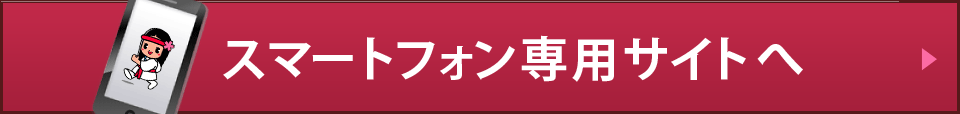














更新日:2024年03月01日