児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母または父、または父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。
支給を受けることができる人(受給資格者)
児童扶養手当を受けることができる人は、下記の要件に当てはまる児童を「監護している母」または「監護し、かつ生計を同じくする父」あるいは「父母にかわってその児童を養育している方」です。
なお、ここでいう児童とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいます。(児童の心身に概ね中度以上の障害がある場合は、20歳までとなります。)
- 父母が婚姻を解消(離婚など)した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が一定の障害(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からの保護命令を受けた児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童 など
次の場合は手当を受けることはできません
- 児童や手当を受けようとする母、父または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき、または児童福祉施設などに入所しているとき
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている、または生計を同じくしているとき
・親族以外の異性と住民票が同地番にある場合や、同居(ルームシェアを含む)している場合、定期的な訪問や生活費の援助がある場合なども手当を受けることはできません。
児童扶養手当の手続き
1.認定請求(最初の手続き)
児童扶養手当の支給を受けるためには、認定請求の手続きが必要です。
- 認定請求の手続きは、 受給資格者ご本人が窓口へお越しください 。(複数回窓口にお越しいただく場合があります)
- 認定できるかどうかの審査には概ね2か月程度かかります。
- 手当は受給資格認定を受けた後、請求された日の属する月の翌月分から支給されます。
・ 適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持の方法などについて、質問、追加資料の提出、調査を実施する場合があります。受給資格の確認で、やむを得ずプライバシーに立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。
手続きに必要なもの
- 請求者および対象児童の戸籍謄本(発行後1か月以内のもの)
・ 離婚の場合は、離婚の記載のある戸籍が必要です。
・提出が月末で、戸籍に離婚の記載がまだできていない場合は、「離婚届受理証明書」にて対応します。記載ができ次第、戸籍の提出をお願いします。 - 請求者の預金通帳
- マイナンバーがわかるもの(請求者および対象児童、同居する家族全員のもの)
- その他(請求者の状況により追加書類が必要となる場合があります)
2.現況届による更新(毎年の手続き)
児童扶養手当を引き続き受給するためには、現況届による更新の手続きが必要です。
- 現況届の手続きは、 受給資格者ご本人が窓口へお越しください 。
- 毎年8月1日から8月31日までが提出期限となります。(届は7月末に郵送します)
- 現況届を提出しないと11月分以降の手当を受給することができません。
- 現況届を2年間提出しない場合は、受給資格が失われます。
・ 適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持の方法などについて、質問、追加資料の提出、調査を実施する場合があります。受給資格の確認で、やむを得ずプライバシーに立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。
3.一部支給停止適用除外事由届の提出
下記の要件に該当する方は、「就業していること」または「就業活動を行っていること」あるいは「就業が困難である事情があること」を届け出ていただくことが必要となります。
届出がない場合や上記に該当しない場合は、手当額の2分の1が支給停止となります。
対象となる方には、事前に通知しますので、提出期限までに必ず提出してください。
≪対象者≫
- 手当の支給開始月の初日から起算して5年を経過した方(認定請求した日において、3歳未満の児童を監護する方は、当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から起算して5年)
- 手当の支給要件(離婚、父(母)の死亡等)に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過した方
・ 上記1と2の到達日が早い方となります。ただし、1の( )に該当する方は、その方法により算出された到達日が適用されます。
児童扶養手当の月額および支給方法
手当の月額
手当の額は、受給資格者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母や兄弟姉妹など)の前年所得と、税法上の扶養する人数に応じた所得制限限度額の規定により「全部支給」「一部支給」「全部停止(支給なし)」が決定します。(1月から9月の間に請求された場合は、前々年所得を確認します。) また、毎年、現況届の提出により11月1日から翌年10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
なお、令和6年11月より制度改正があり、次のとおりになりました。
≪令和7年4月から≫
| 対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
| 1人目 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
| 2人目以降(加算額) | 11,030円 | 11,020円~5,520円 |
・ 受給資格者または対象児童が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給できる場合は、児童扶養手当額と公的年金の支給額の差額分が支給されます。
(厚生労働省リーフレット) (PDF:397.6KB) (PDFファイル: 397.7KB)
・ 児童扶養手当を受給しており、公的年金を遡って受給されるようになった場合は、それに合わせて児童扶養手当の返還が必要となります。
一部支給の場合は、次の計算式により計算します。(10円未満四捨五入)
【1人目】=45,490円-(「A」-「B」)(注)0.025
【2人目以降】=10,740円-(「A」-「B」)(注)0.0038561
「A」:受給資格者の所得額、 「B」:全部支給の所得制限限度額
・ 「A」「B」の数字(計算方法)については、下段の「所得制限」をご覧ください。
手当の支給方法
手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給され、請求者の指定された金融機関の口座へ年6回振り込まれます。(支払日前の通知はありませんので、通帳の記帳でご確認ください。)なお、必要な手続きをされていない場合は、手当が差し止められたり、手当の支給が遅れたりしますので、必ず手続きを行ってください。
| 支払期 | 1月期 | 3月期 | 5月期 | 7月期 | 9月期 | 11月期 |
| 支払日 | 1月11日 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 |
| 対象月 | 11~12月分 | 1~2月分 |
3~4月分 |
5~6月分 | 7~8月分 | 9~10月分 |
所得制限
受給資格者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母や兄弟姉妹など)の所得額が下表「所得制限限度額表」の金額に満たない場合は、その金額に応じて「全部支給」「一部支給」となります。
所得の計算方法
下記の計算式に当てはめて算出します。
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等) +養育費等の8割分 -80,000円-諸控除
・所得額は前年のものになりますので、離婚されてすぐに認定請求される際は養育費等の8割分は加算されません。
・総所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、その合計額から10万円を控除します。(給与所得及び公的年金等に係る所得分に限ります)
| 勤労学生控除 | 270,000円 | 配偶者特別控除 | 住民税で控除されている額 |
| 障害者控除 | 270,000円 | 雑損控除 | |
| 特別障害者控除 | 400,000円 | 医療費控除 | |
| 寡婦(夫)控除 | 270,000円 | 小規模企業等掛金控除 | |
| 特別寡婦控除 | 350,000円 |
・ 受給資格者が、父母である場合は寡婦(夫)控除および特別寡婦控除は控除しません。
所得制限限度額
上記の計算式で算出した所得が、下図の記載金額に満たない場合は手当が支給されます。(受給資格者は「一部支給停止」の金額)
| 扶養親族等の数 | 請求者 |
孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
| 全部支給 | 一部支給停止 | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
|
加算額(1人につき) |
老人控除対象配偶者・老人扶養親族:100,000円 特定扶養親族(税法上と異なる):150,000円 |
老人扶養親族:60,000円 (扶養親族と同数の場合は1人を除く) |
|
・所得は、世帯全員の合算でなく、個々の所得で判定します。
「請求者」の所得額が、一部支給停止の所得制限限度額未満で、かつ「扶養義務者(同居している請求者の父母や兄弟姉妹など)等」も所得制限限度額未満である場合に、手当が支給されます。
こんなときは必ず手続きしてください
1.受給資格がなくなったとき
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。すみやかに担当課へ届出をしてください。届出をしないまま手当を受けていると、受給資格のなくなった月の翌月分から受給していた手当は、全額返還していただくことになります。
- あなたが児童の母(父)であった場合で、あなたが婚姻した場合(事実婚など同居等が含みます)
- あなたが児童の母(父)以外の養育者の場合で、あなたと児童が別居したとき
- あなたが児童の母(父)以外の養育者の場合で、児童が、児童の父(母)と同居するようになったとき(一定の障害(国民年金の障害等級1級相当)の状態にあるときを除く)
- あなたが児童を監護しなくなったとき
- あなたや児童が日本国内に住所を有しないとき
- あなたや児童が死亡したとき
- 遺棄していた母(父)から連絡や仕送りがあったとき
- 児童が児童福祉施設に入所したときや、里親に委託されたとき・・・・・など
2.手当の支給対象となる児童の数が増えたとき。または減ったとき。
3.あなたや児童の氏名が変わったとき
4.住所変更したとき
5.受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居になったとき
6.あなたや同居している扶養義務者の所得が変更されたとき
7.手当を受ける金融機関が変わるとき
8.手当を受けることになった理由が変わるとき
9.あなたや児童が公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき
10.児童が、父または母に支給される障害年金などの額の加算対象になったとき
児童扶養手当の適正な受給のために
児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与するとともに、ひとり親家庭の自立を促すことを趣旨として、貴重な税金をもとに支給しています。趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い適正に行っていただく必要があります。
1.調査の実施について
児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持の方法などについて、質問、追加資料の提出、調査を実施する場合があります。受給資格の確認で、やむを得ずプライバシーに立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。
【根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項】
2.手当の全部または一部を支給しないことがあります
児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。
【根拠法令:児童扶養手当法第14条】
3.手当の支給を差し止める場合があります
必要な手続きや書類の提出が無い場合は、手当の支払を差し止めることがあります。
【根拠法令:児童扶養手当法第15条、同法第28条第1項】
4.不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます
偽りの申告や不正な手段で手当を受給した場合は、支給した手当を返還していただくことがあります。また、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
【根拠法令:児童扶養手当法第23条第1項、同法第35条】
お問い合わせ
桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 手当係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2212)
ファックス:0744-48-5175
メールフォームによるお問い合わせ
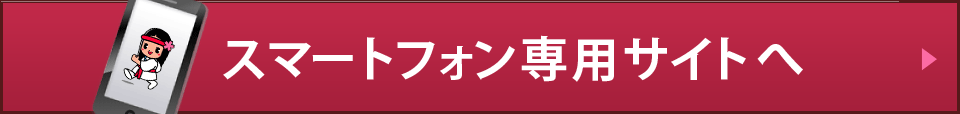














更新日:2025年04月01日