【たべもの】三輪そうめん
たべもの
三輪そうめん
「大和三輪素麺 名物なり 細きこと糸の如く 白きこと雪の如し ゆでてふとらず 余国より出づる そうめんの及ぶ所にあらず」(日本山海名物図絵1754年)
そうめんの里 三輪
厳選された最上質の小麦、そして神々の時代から培われてきたといわれる手作りの技。これらの調和によって生み出された手延べそうめんが、風味豊かな伝統の味で全国に知られる「三輪そうめん」なのです。底冷えのする盆地の寒さと、からりと晴れた冬の空が、糸のように細く歯ざわりのよいそうめんを作り出します。
風土が生んだ味の傑作、それが三輪素麺。長い歴史が伝統の味になり、磨かれた技が独特の風味を生みました。
『桜井市史』 第4章工業より
『桜井市産業名鑑』(1977年)によれば、本市の手延素麺業者は95戸(うち販売のみ2戸を含む)、その他に麺類(うどん)業者7戸、製麺業1戸、はるさめ業者6戸がある。とくに手延素麺は「三輪そうめん」と呼はれ、全国的に名声を博している。
産地
大正三年(1914年)当時をみると、すでに業者は現在の桜井市域に集中しており、とくに初瀬川に沿う三輪地区を中心に、巻向川沿いの織田・巻向地区、寺川・粟原川沿いの桜井・城島地区に多くみられた。現在の業者数は、盛時と比べると著しく減少しており、大正三年当時の四分の一近くになっている。しかし、業者の分布地域には大きな変動がなく、主産地は三輪・織田・巻向・桜井の諸地区となっている。 それら産地の形成に、当初水車の分布が密接に関係したとみられる。 明治初年に水車の数は30個あったといわれ、三つの河川系統に属していた。 すなわち、初瀬川水系、巻向川水系、寺川・粟原川水系である。水車の約半数は、そうめん粉の製粉を行っており、その位置関係から多武峯を水源とする寺川・粟原川の水車は三輪・桜井地区、巻向川水系の水車は織田・巻向地区の業者の製粉を請け負っていた。 水車は江戸時代に発達し、明治期にピークに達したが、やがて大和高原の西縁部に関西水力電気・初瀬水力電気などの開発によって衰退し、昭和初期には数個を数えるのみとなった。水車利用のほかに立地条件として、付近に粘性に富む良質の小麦が栽培されていたこと、製造期の冬季のきびしい寒さと晴天日数の多いこと、農閑期の余剰労働力の存在などがあげられる。
歴史
三輪そうめんの由来については、古い伝承がある。 大物主命の後裔で、大神神社の宮司大神朝臣狭井久佐(おおみわのあそんさいくさ)の次男穀主(たねぬし)が、三輪の里の地味が小麦の栽培に適しているのを知り、種を蒔かせその小麦を原料にして三輪そうめんを作り、地域の生業を発展させようとしたのが始まりであるといわれる(大神神社史料)。 そして、『日本山海図絵』(宝暦四年版)に、「大和三輪素麺、名物なり、細きこと糸のごとく、白きこと雪の如し、ゆでてふとらず、余国より出づる素麺の及ぶ所にあらず……旅人をとむる旅籠やにも名物なりとて素麺にてもてなすなり」と紹介されてから、全国にその名が知られるようになったといわれる。
明治二十八年(1895年)、素麺業組合取締規則の施行によって三輪素麺組合が結成され、その後同三十三年に素麺業組合法の制定で三輪素麺同業組合に改められた。 県下全域をその範囲とし、原料の精選、製品・容器・荷造り検査、販路拡張などを活動目的とし、品質管理と業界発展に寄与するところが大きかった。 三輪そうめん製造は、明治三十年ごろから大正期を経て昭和十四、五年ごろまでが全盛期で、製造戸数も300戸前後に達した。 生産量もほぼ戸数に比例しており、大正十二年の114,222万箱をピークとして、昭和十五年ごろまで七万箱前後のあいだを上下していた。
第二次世界大戦中は、原料の小麦が主食に入るため食料統制を受けて沈滞し、休業者が続出して生産量は激減した。
戦後になって、諸統制が撤廃され、自由営業が復活した。やがて協同組合法によって三輪素麺工業協同組合が設立され、組合加入者は「三輪そうめん」の商標で販売することを許可されている。 近年小麦粉に天然の卵黄を混ぜた玉子そうめん、抹茶とクロレラを混ぜた茶そうめんなどの色そうめんが開発され、味と香気を添えた栄養価と風味の高いものが作られている。
製造工程と流通
三輪そうめんの製造期間は極寒の12月1日から翌年3月末日までと三輪素麺工業協同組合で決められている。 その他の期間では暖かくて良質のそうめんができないからである。 しかし最近では、需要に供給が追いつかず、11月10日から翌年4月末日まで延長されているのが実状である。
製造工程は二日間にわたって行われる。 第一日目の工程は午前四時半に始まり、午後六時に終わる。第二日目は午前七時から午後四時までで、全工程を終了する。 この二日間の工程を繰り返し連続して期間中作業を行う。 製造工程に二日がかりで、ゆっくり時間を掛けて十分にグルテン(粘りけ)を変化させ、その最高の状態をうまく利用して仕上げるという長い間に培われた伝統の技術が三輪そうめんの特徴となっている。
製品には、極細の最高級品神杉(かみすぎ)から、緒環(おだまき)、瑞垣(みずかき)、誉(ほまれ)、戎(えびす)などがある。 戎でも播州の「揖保(いぼ)の糸」あるいは小豆島の「島の糸」と同級とされている。 そうめんの製造は、12月1日から翌3月末までの農閑期の120日間に行われ、夏そうめん製造の7~8月間を入れても、うまく農事暦の中に組み込まれている。すなわち農家の副業として成り立っているのである。
手延三輪そうめん製造工程(現在は機械化されている部分がある)
1日目工程
午前4時半
- なかだち (塩水づくり)
- こね (小麦粉と塩水のみでこねる、団子踏み、のし餅状にする、外側より渦巻状に切る)

こねまえ・板切作業
- いたぎ (板状にのばす)
7時
油がえし (油をまんべんなくぬる)

油返し (3~4時間熟成)
11時
- ほそめ (約1センチメートルの細さにする)

細め・小撚作業
- こより (約5ミリメートルの細さにする)
(約1時間熟成)
- かけば (2本のくだに8の字にかける)

掛巻作業 (約30分間熟成)
午後6時
- こびき (約35センチメートル引きのばす)

小引作業
2日目工程
7時
・かどぼし(前日のもの)

かどぼし・乾燥作業 ↓
- こわり取り (取入れ)
午後6時
- こわり (裁断)

裁断・結束作業

出荷
お問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3623・3622)
ファックス:0744-48-0271
メールフォームによるお問い合わせ
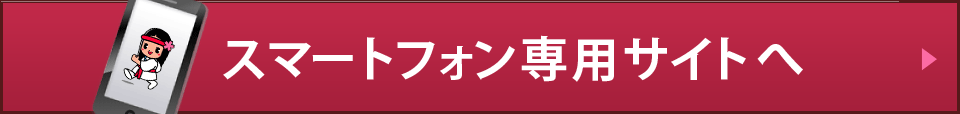














更新日:2022年03月01日