所得控除
医療費控除
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制のいずれかを選択適用します。
従来の医療費控除
納税義務者本人やその扶養親族のために医療費を支払った場合、次の計算式で計算した金額が控除額です。 控除額=支払った医療費‐保険等により補填された金額‐総所得金額×5%または10万円のいずれか低い金額
申告に必要な証明書類
- 医療費控除の明細書
- 病院や薬局などの領収書
- 保険組合等から送られる医療費通知
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康の維持増進及び疫病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行っている個人が本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品」の購入費用を1年間に12,000円以上支払った場合には、12,000円を超える額(控除限度額88,000円)を所得控除できる特例が創設されました。対象期間は平成29年1月1日(平成30年度課税)から令和8年12月31日(令和9年度課税)までです。 適用を受けるためには、申告する方が、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として以下のような取組を行っている必要があります。なお、健診等にかかった費用は医薬品等の購入費用に含めることはできません。
- 健康保険組合や国保が実施する人間ドッグ、各種健(検)診等
- 生活保護受給者等を対象とする健康診査
- 予防接種(定期接種、インフルエンザの予防ワクチン)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
- 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が実施するがん検診
(注)スイッチOTC医薬品とは、医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用された、薬局で購入できる市販の医薬品のことです。対象の薬品には、領収書に控除対象であることが記載されています。
(注)従来の医療費控除との選択適用となります。
申告に必要な証明書類
- セルフメディケーション税制の明細書
- 医薬品購入時の領収書
- 健診等の受診を証明する書類
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金
納税義務者本人やその扶養親族の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料・その他健康保険料等や小規模企業共済等を支払った場合、支払額全額が控除額となります。
申告に必要な証明書類
領収書、控除証明書など
生命保険料控除
納税義務者が支払った生命保険料・個人年金保険料または介護医療保険料がある場合、表の計算式の金額が控除額です。
生命保険の種類と内容
一般生命保険料
生存又は死亡に起因して保険金が支払われるものです。
介護医療保険料
医療費の支払に起因して保険金等が支払われるものです。
個人年金保険料
年金の給付を目的とし、かつ年金以外の支払は被保険者が死亡又は重度障害に限り行われるものです。 (注)契約内容により控除の対象とならない場合があります。
各生命保険料控除額の計算方法
新契約に係るもの
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| ~12,000円 | 支払保険料等の全額 |
| 12,001円~32,000円 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
| 32,001円~56,000円 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
| 56,001円~ | 一律28,000円 |
(注)新契約とは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約のことです。
旧契約に係るもの
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| ~15,000円 | 支払保険料等の全額 |
| 15,001円~40,000円 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
| 40,001円~70,000円 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
| 70,001円~ | 一律35,000円 |
(注)旧契約とは、平成23年12月31日までに締結した保険契約のことです。
各生命保険料控除額の限度
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除、介護医療保険料控除を合わせた制度全体の適用限度額は70,000円です。
一般生命保険料、個人年金保険料
新契約に係るもの 28,000円
旧契約に係るもの 35,000円
介護医療保険料
28,000円
申告に必要な証明書類
控除証明書
地震保険料控除
納税義務者が支払った地震保険料または長期損害保険料がある場合、表の計算式の金額が控除額です。
地震保険料控除額の計算方法
| 保険料等の 区分 | 支払った保険料の金額 | 地震保険料控除額 |
|---|---|---|
| 地震保険料 | ~50,000円 | 支払った保険料×0.5 |
| 50,001円~ | 25,000円 | |
| 旧長期損害保険料 | ~5,000円 | 支払った保険料の全額 |
| 5,001円~15,000円 | 支払った保険料×0.5+2,500円 | |
| 15,001円~ | 10,000円 |
(注)保険契約が両方ある場合には、合計額で25,000円を限度額とします。
(注)1契約のうち、保険料等の区分がいずれにも該当するときは、いずれか一方の契約のみに該当するものとして計算します。
申告に必要な証明書類
控除証明書
障害者控除
納税義務者本人又は扶養親族が障害者に該当する場合の控除です。
一般障害者控除
控除額
26万円
対象者
- 身体障害者手帳3級~7級の方
- 精神障害者手帳2級~7級の方
- 療育手帳Bの方
特別障害者控除
控除額
30万円(同居している扶養親族の場合は23万円加算)
対象者
- 身体障害者手帳1級~2級の方
- 精神障害者手帳1級の方
- 療育手帳Aの方
申告に必要な証明書類
障害者手帳
寡婦控除
納税義務者本人の合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない方が、次のいずれかに該当する場合、26万円の控除があります。
- 夫と死別・離婚後再婚をしていないか、夫が生死不明で、扶養親族を有する場合
- 夫と死別後再婚をしていないか、夫が生死不明で扶養親族を有していない場合
ひとり親控除
納税義務者本人の合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない方が、次のいずれにも該当する場合、30万円の控除があります。
- 配偶者と死別・離婚後再婚をしていないか、配偶者が生死不明の方
- 前年の総所得金額等が48万円以下(令和8年度以降は58万円以下)の生計を一にする子を有する。ただし、その生計を一にする子が他の者の扶養親族である場合を除く。
勤労学生控除
納税義務者が学生で、かつ合計所得金額が75万円以下(令和8年度以降は85万円以下)であり、そのうち、自己の勤労による所得以外の所得が10万円以下の場合、26万円の控除があります。
申告に必要な証明書類
学生証、卒業証書など
配偶者控除
納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の年間(1月~12月)の合計所得金額が48万円以下(令和8年度以降は58万円以下)の方がいる場合に適用できます。
(注)他の方の扶養親族または事業専従者に該当する方は除きます。
(注)配偶者控除には、いわゆる内縁関係は含まれません。
(注)納税義務者の所得が1,000万円を超える場合であっても、控除額はありませんが、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下(令和8年度以降は58万円以下)の場合「同一生計配偶者」として扶養親族等の人数には含まれます。
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
| 58万円以下 | 33万円(38万円) | 22万円(26万円) | 11万円(13万円) |
(注) ( )は老人の配偶者控除額(70歳以上)
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
| 48万円以下 | 33万円(38万円) | 22万円(26万円) | 11万円(13万円) |
(注) ( )は老人の配偶者控除額(70歳以上)
配偶者特別控除
- 納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の年間(1月~12月)の合計所得金額が48万円超 133万円以下(令和8年度以降は58万円超 133万円以下)の場合に適用できます。
(注)他の方の事業専従者に該当する方は除きます。
(注)配偶者特別控除には、いわゆる内縁関係は含まれません。
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
| 58万円超 100万円以 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 | 対象外 | ||
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
| 48万円超 100万円以下 |
33万円 |
22万円 | 11万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 |
26万円 |
18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 | 対象外 | ||
扶養控除
納税義務者と生計を一にする親族で年間(1月~12月)の合計所得金額が48万円以下(令和8年度以降は58万円以下)の方がいる場合に適用できます。
(注)他の方の扶養親族または事業専従者に該当する方は除きます。
一般扶養控除額
33万円
特定扶養控除額(19~22才)
45万円
令和7年度税制改正により、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)が創設されました。
対象となる扶養親族の合計所得金額が58万円を超えても123万円までの範囲で合計所得金額に応じて控除が受けられます。特定親族特別控除は令和8年度以降に適用されます。
| 給与収入ベース | 合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
| 123万円超160万円以下 | 58万円超95万円以下 |
45万円 |
| 160万円超165万円以下 | 95万円超100万円以下 |
41万円 |
| 165万円超170万円以下 | 100万円超105万円以下 |
31万円 |
| 170万円超175万円以下 | 105万円超110万円以下 |
21万円 |
| 175万円超180万円以下 | 110万円超115万円以下 |
11万円 |
| 180万円超185万円以下 | 115万円超120万円以下 |
6万円 |
| 185万円超188万円以下 | 120万円超123万円以下 |
3万円 |
老人扶養控除額(70才以上)
38万円
同居老親扶養控除額(70才以上で直系尊属)
45万円
年少扶養控除額(16才未満)
0円
(注)平成24年度から年少扶養の控除額は廃止されましたが、市・県民税の非課税限度額の算定に使用するため、申告が必要です。
基礎控除
合計所得金額が2500万円以下の納税義務者である場合に適用できます。
- 2,400万円以下の場合
基礎控除は43万円 - 2,400万円超2,450万円以下の場合
基礎控除は29万円 - 2,450万円超2,500万円以下の場合
基礎控除は15万円 - 2,500万円超の場合
基礎控除はありません。
お問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1722・1723)
ファックス:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ
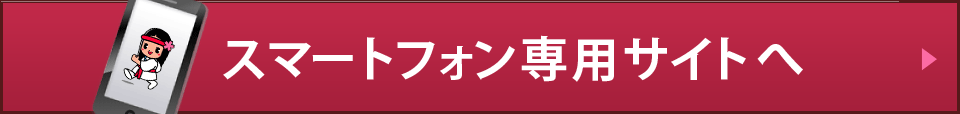














更新日:2025年12月25日