介護保険制度
介護保険制度は、介護が必要になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した生活を送れるよう支援するものです。介護を必要とする人の選択により、多様な事業者から保健・医療・福祉のサービスを総合的に受けることができます。 平成29年4月1日から桜井市介護予防・日常生活支援総合事業(以下総合事業)がスタートしました。総合事業は、要介護認定区分をお持ちでなくても、25項目からなる簡単な基本チェックリストをして、事業対象者に該当すれば、必要性に応じて介護予防のための事業サービスを利用することができます。事業サービスでは平成30年3月31日をもって廃止された介護予防訪問介護・介護予防通所介護に相当するサービスも実施されています。
桜井市介護予防・日常生活支援総合事業についてはこちらへお進みください
介護サービスを利用するには(認定申請)
被保険者が日常生活に支援が必要な状態になったとき、市役所高齢福祉課に要介護認定等の申請をします。要介護認定の結果によって利用できるサービスが変わります。在宅サービスを利用するには、ケアマネジャーに介護サービス計画作成を依頼する必要があります。
介護サービス計画とは、利用者の希望や家族の状況などに応じてサービスの内容や必要器具の手配などを決める時間割のようなものです。サービス利用までの流れ
(1) 高齢福祉課窓口で認定申請をします
申請に必要なもの
- 第1号被保険者(65歳以上の方)は介護保険被保険者証、第2号被保険者(40歳から64歳の方)は 加入している医療保険の被保険者証
- 本人のマイナンバーを確認することができる書類(通知カード等)
- (申請書に記入するために)かかりつけの医療機関名・主治医名がわかるもの
地域包括支援センターや介護事業所に代理申請を依頼することもできます。
(2)心身の状態を調査します
- 認定調査
調査員が自宅等に訪問し、本人や家族などから聞き取り調査等を行います。 - 主治医意見書
申請時に指定した主治医が、意見書を作成します。
(3)どのくらい介護が必要か審査し、認定します。
- 審査・判定
認定調査の結果と主治医意見書を元に、福祉・保健・医療の専門家から構成される介護認定審査会(桜井宇陀広域連合)が、どのくらい介護が必要か審査・判定します。 - 認定
介護認定審査会の判定をもとに、要介護度の認定が行われます。
(4)「介護保険被保険者証」と「要介護認定結果通知書」が届きます。
在宅サービスを利用する際は、ケアマネジャーに介護サービス計画(ケアプラン)作成を依頼する必要があります。ただし結果が非該当の場合は介護予防サービまたは介護サービスを利用することはできません。
要介護認定とは
調査員が訪問し心身の状況などを聞き取りながら確認し、全国共通の調査票に記入します。介護認定審査委員会が調査票に基づいた一次判定結果や主治医の意見書などをもとに、介護の必要性とその程度の判定をします。認定結果は主治医の意見書と、認定調査票の両方の書類がそろってから約2週間後に審査決定されます。
新規の認定申請や区分変更申請で認定された介護区分の有効期間は「申請日」から適用されます。そのため認定申請から結果が通知されるまでの間に、サービスが必要な場合については、認定結果を見越して、暫定の介護サービス計画に基づいて介護サービスの利用をすることができます。ただし、見越した要介護区分が認定されなかった場合には、利用者負担が増えたり、全額利用者負担となる場合があります。また認定の有効期限は原則6ヶ月ですが、同じような状態が続く場合は最長3年になります。
[要介護認定の種類]右に行くほど重い
要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5
要支援1・2または非該当と認定された方は
地域包括支援センターが中心となって介護予防ケアマネジメントを行います。
要支援:1・2と認定された方は、介護保険の介護予防サービスと桜井市が実施する総合事業のサービスを利用することができます。また、非該当で、介護予防に取り組みたい方は、一般介護予防事業を利用することができます。どちらのサービスも地域包括支援センターが中心となって、住みなれた地域でいつまでも自立した生活を続けていけるようサポートしていきます。
地域包括支援センター
在宅の要支援・要介護となるおそれのある高齢者と、その家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、ニーズに対応した保健、福祉サービスが総合的に受けられるように電話相談・面接相談等をしています。また、介護予防事業とし、様々なサービスを提供していきます。
| 担当校区 | 名称 | 所在地・電話番号 |
|---|---|---|
| 桜井中学校 | 桜井市地域包括支援センター のぞみ | 大字阿部1070番地 電話番号 42-5590 |
| 桜井東中学校 | 桜井市地域包括支援センター きずな | 大字出雲1642番地 電話番号 44-3655 |
| 大三輪中学校 | 桜井市地域包括支援センター ひかり | 大字大豆越104番地の1 電話番号 45-3651 |
| 桜井西中学校 | 桜井市地域包括支援センター きぼう | 大字阿部323番地 電話番号 46-1023 |
以上4ヶ所に委託しています。相談は無料です。
要介護1~5と認定された方は
利用を開始する前に、居宅介護支援事業者などと契約し、サービスの内容を具体的に盛り込んだ介護サービス計画(ケアプラン)を作成することが必要です。 契約する居宅介護支援事業所は利用者自身で選びます。
介護サービス(在宅サービスと施設サービス)
福祉用具の貸し出しのほか、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、介護や家事の援助をする訪問介護や医師の指示のもと看護師などが訪問する訪問看護、日帰りで施設等へ通所するデイサービス・デイケア、短期間入所するショートステイなどがあります。
施設サービス介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、家庭での介護が困難なねたきりや認知症の方を主に介護している施設です。介護老人保健施設では比較的病状が安定した方で介護や看護を必要とする方に対し、医学的な管理のもとで介護やリハビリテーションを行う施設などがあります。
住宅改修は、事前申請が必要です。
事前に「住宅改修が必要な理由書」等の書類を市に提出し、審査を受ける必要があります。ケアマネジャーにご相談ください。担当のケアマネジャーがいない場合は、福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者を配置している工務店等に直接ご相談ください。
事前申請なく施工された改修は介護保険給付の対象になりません。
福祉用具購入は、県指定事業者に限られます。
県指定の特定福祉用具取扱事業者で購入した場合に限り、介護保険給付の対象になります。
ケアマネジャーにご相談ください。担当のケアマネジャーがいない場合は、直接特定福祉用具販売事業所に連絡してください。
ホームセンター等で購入された場合は介護保険給付の対象になりません。
介護サービスを利用したときの利用者負担
所得に応じてかかった費用の1割から3割(3割は平成30年8月サービス利用分から)を負担します。また、施設サービスなどを利用した場合には、介護サービス費の他に食費や部屋代などの負担があります。自己負担の割合は認定結果と同時に郵送される「介護保険負担割合証」(オレンジ色)(注)でご確認ください。
(注)令和7年度(有効期限令和7年8月1日~)から「介護保険負担割合証」はピンク色に変更しています。
2割負担の方
本人の合計所得金額が160万円以上かつ年金収入+その他の合計所得が単身で280万円以上の方(65歳以上複数世帯の場合は346万円以上)
3割負担の方
本人の合計所得金額が220万円以上かつ年金収入+その他の合計所得が単身で340万円以上の方(65歳以上複数世帯の場合は463万円以上) その他、介護費用が高額になったときの利用者負担の軽減や、災害等による利用負担の減額などの制度があります。
介護保険料の納付について
1) 第1号被保険者(65歳以上の方)
介護保険料は、基準額をもとに、所得の低い方などの負担が大きくならないよう本人や世帯の課税状況、所得などに応じて決まります。また、3年ごとの介護保険事業計画の見直しに伴い保険料基準額が改定されます。 第1段階の方は2015年から消費税による公費を投入し、調整率を0.5から0.45に負担軽減、2019年からは消費税率10%への引き上げに合わせて、公費投入による保険料の負担軽減の対象者を1~3段階の方に広げ、段階的に負担軽減を実施しています。
桜井市第6期介護保険料(平成27年度から平成29年度) (PDFファイル: 106.2KB)
桜井市第7期介護保険料(2018年度から2020年度) (PDFファイル: 99.4KB)
桜井市第8期介護保険料(2021年度から2023年度) (PDFファイル: 212.2KB)
桜井市第9期介護保険料(2024年度から2026年度) (PDFファイル: 445.1KB)
2) 第2号被保険者(40歳から64歳の方)は
加入している医療保険料として支払います。国民健康保険に加入している方は、被保険者数等に応じて異なります。健康保険や共済組合などに加入している方は、総報酬額等に応じて異なり、半額は事業主が負担します。
3)保険料の納付が困難になったら
災害による損害など特別な事情により保険料の納付が一時的に困難になった方は、手続きをすることで保険料が減額される場合があります。
介護保険料の納付方法は
1) 第1号被保険者(65歳以上の方)
以下のいずれかとなります。
- 特別徴収
老齢・退職・障害・遺族等の年金を年額18万以上受給している方は、年金から天引きされます。 - 普通徴収
特別徴収以外の方は、口座振替または納付書により市役所や金融機関で納めます。
2) 第2号被保険者(40歳から64歳の方)
国民健康保険や健康保険組合・共済組合などに社会保険料として納めます。国民健康保険の方は、口座振替または納付書により市役所や金融機関などで納めます。職場の健康保険組合・共済組合などに加入している方は、給料から天引きされます。
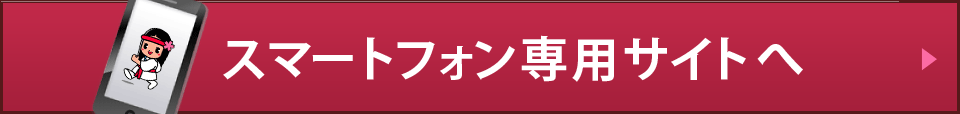














更新日:2022年07月01日