保育所・認定こども園・小規模保育事業所・家庭的保育事業所について
支給認定について
1号認定・2号認定・3号認定について
お子さまが幼稚園や、保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所をご利用になる際には、まず支給認定を受ける必要があります。 支給認定は、どれだけの期間、どれだけの量、保育施設を利用する資格があるかということを認定するもので、入所の申請をする際に必要となります(支給認定証は、保育施設の利用決定通知ではありませんのでご注意ください)。 認定の種類と利用可能施設は以下のとおりです。
| 認定区分 | 対象 | 主な利用施設 |
| 1号認定 |
満3歳以上の小学校就学前の お子さまで学校教育のみを受ける場合 |
幼稚園・認定こども園 の教育部分 |
| 2号認定 |
満3歳以上の小学校就学前の お子さまで保育を必要とする場合 |
保育所・認定こども園 の保育部分 |
| 3号認定 |
満3歳未満のお子さまで 保育を必要とする場合 |
保育所・認定こども園・小規模保育事業所・家庭的保育事業所 |
保育を必要とする事由について
保育を必要とする事由とは、具体的には以下の事由を指します。
就労(月64時間以上の就労が必要)
妊娠・出産
保護者の疾病・障がい
親族の常時介護・看護
災害復旧
求職活動
就学
育児休業取得中の継続保育利用
保護者をはじめ、同居する親族等全員(20歳以上65歳未満の同居人)に保育を必要とする事由がない場合、2号認定、3号認定を行うことはできません。
支給認定期間について
保育を必要とする事由により、認定期間が異なります。また、途中で保育を必要とする事由がなくなれば認定期間は終了します。認定期間が終了すれば、保育施設を利用することはできません。
なお、お子さまが満3歳未満の場合、最長で「お子さまが満3歳に到達する前日まで」の支給認定証(3号認定)が交付されます。満3歳以上になっても保育を必要とする事由が継続している場合、2号認定へ変更する新たな支給認定証を交付します。
保育の必要量について
保育施設を利用する際には、保護者の状況に応じ、保育を受けられる必要量を認定します。認定区分は「保育標準時間」(1日に最大11時間までの利用)と「保育短時間」(1日に最大8時間までの利用)の2種類に分けられます。原則、保護者が1ヶ月あたり120時間以上の就労をされている場合等に、保育標準時間と認定します。
保育施設によって、利用時間が異なりますので、詳しくは各保育施設へお尋ねください。
保育を必要とする事由と必要量、認定期間について
支給認定を受けた後に、保育を必要とする事由の変更や、内容の変更(就労時間の変更や転職など)があった場合は、保育教育課の窓口で、速やかに手続きが必要です。毎月10日(土日祝日の場合は前開庁日)締切で翌月から支給認定の変更を行います。
| 保育を必要する事由 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 認定期間 |
| 就労 | 可 | 可 | 小学校就学の始期に達するまでの期間 |
| 妊娠・出産 | 可 | 可 | 出産予定月の前2ヶ月から、出産月の後2ヶ月までの期間 |
| 疾病・障害がい | 可 | 可 | 保護者の疾病等が快復・平癒した日の月末、又は小学校就学の始期に達するまでの期間 |
| 親族の常時介護・看護 | 可 | 可 | 介護・看護が終了する日の月末、又は小学校就学の始期に達するまでの期間 |
| 災害復旧 | 可 | 可 | 災害復旧し、保育の必要がなくなった日の月末、又は小学校就学の始期に達するまでの期間 |
| 求職活動 | 可 | 不可 | 利用開始後3ヶ月が経過する日が属する月の末日までの期間 |
| 就学 | 可 | 可 | 卒業(修了)予定日が属する月の末日までの期間 |
| 育児休業取得中の継続保育利用 | 可 | 不可 | 原則、生まれた子が満1歳に達する日の属する月の末日までの期間(入所保留による育児休業期間の延長時は除く。) |
保育施設の入所(2号認定・3号認定)の流れ
申請(支給認定申請と施設利用申請)
保育施設への入所を初めて希望する場合、申請期間内に支給認定申請と、保育施設の利用申請を同時に行う必要があります。申請についての詳細は、該当年度の利用案内をご覧ください。
支給認定
支給認定申請を基に、支給認定を行います。認定結果は、特に希望がない場合、保育施設への入所決定後に支給認定証として交付します。事前に支給認定証の交付を希望する場合は、保育教育課にお問い合わせください。
ただし、支給認定証は保育施設への入所決定を意味する書面ではありません。
利用調整
施設利用申請を基に、保育施設への入所の可否を判断します。施設の受入可能数に余裕がある場合は入所することができますが、希望者が受入可能数を超えている場合、利用調整を行います。利用調整終了後、入所の可否について書面で通知します。利用調整の結果、不承諾(入所保留)となった場合は、利用希望月には入所することができません。
不承諾(入所保留)後の流れについて
不承諾(入所保留)となった場合は、同一年度内であれば翌月以降も継続して利用調整を行います(保育を必要とする事由を失っている場合や、取り下げを行った場合等は除く。)。ただし、翌年度も入所を希望される場合は、申請期間内に改めて申請する必要があります。
例えば、令和6年度の施設利用申請を行い、令和6年4月入所の調整結果が不承諾(入所保留)となった場合でも、支給認定期間内であれば、自動的に令和6年5月入所の調整対象となります。しかし、年度の最終月である令和7年3月入所の調整結果が不承諾となった場合、令和7年4月の入所の調整では調整対象となりません。令和7年4月の利用調整対象となるには、改めて令和7年度の施設利用申請が必要となります。
新年度の施設利用申請は毎年10月より配布及び申請となりますので、ご注意ください。
保育料について
幼児教育・保育の無償化
3歳から5歳(小学校就学前まで)のお子さま、市区町村民税非課税世帯の0歳から2歳のお子さまを対象に、幼児教育・保育が無償となります。
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから実施されます。
保育の必要であることの認定を受け、保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所に入所している場合は、原則、無償化のための申請は不要です。
保育料の算定について
保育料は原則、父母の市区町村民税所得割額の合計額に応じて算定されます。また、祖父母が同居する場合で父母の年収合計が130万円未満の場合、祖父母の市区町村民税所得割額も合計されます。通常4月から8月までの保育料は前年度の市区町村民税所得割額(一昨年中の所得に対する課税)に基づいて算定を行い、9月から翌年3月までの保育料は今年度の市区町村民税所得割額(昨年中の所得に対する課税)に基づいて算定されます。なお、保育料の決定に用いる市区町村民税は税額控除(住宅借入金等特別控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、寄付金税額控除、外国税額控除等)の適用を受ける前の税額です。
未申告等で税額の確認ができない場合は、保育料を最高金額で決定しますので、速やかに申告を行ってください。
保育料は月額算定を行っており、日割り計算は行いません。
保育料算定上の年齢は、該当年度の初日の前日の満年齢(クラス年齢)です。
同一世帯において2人以上の小学校就学前のお子さまが保育所等を利用している場合は利用中の第2子のお子さまの保育料が半額、第3子以降のお子さまの保育料が無料になります。
保護者の市町村民税所得割額の合計額によって、就学前であった年齢上限が撤廃され、同居別居にかかわらず生計を一にするきょうだいを人数に数える場合や第2子のお子さまが無料となる場合があります。詳しくはお問い合わせいただくか、該当年度の利用案内をご覧ください。
ひとり親世帯や在宅障がい者世帯(世帯員に障がいをお持ちの方がいる世帯)等の保育料については、軽減措置を受けられる場合があります。書類の提出等が必要となりますので詳しくはお問い合わせください。
桜井市外にお住まいの方で、桜井市内の保育施設に入所する方の場合、保育料の算定はお住まいの市区町村で行います。保育料算定についての質問はお住まいの市区町村にお問い合せください。
保育料一覧表(2号・3号) (PDFファイル: 113.9KB)
給食費について
給食費(主食費・副食費)の徴収について
3歳児(1号認定のお子さまは満3歳から)から5歳児までのお子さまについては幼児教育・保育無償化により、保育料は無料になりますが、給食費(主食費と副食費)の実費徴収分は原則かかります。なお、0歳児から2歳児までの給食費は保育料に含まれます。このことから、3~5歳児クラスのお子さま(1号認定のお子さまは満3歳から)は、給食費(主食費と副食費)をお通いの幼稚園や保育所にお支払いいただくこととなります。
主食費とは米やパン等のことで、副食費とは、おかず、おやつ、牛乳、お茶等です。
給食費(副食費)の徴収免除について
副食費については、所得や世帯の状況が下記に該当する場合は副食費の徴収が免除となります。申請は不要です。徴収免除対象者となった方には、通知を送付いたします。
副食費の徴収免除の判定については、保育教育課が現在把握している課税状況や世帯状況等に基づき行っており、課税状況や世帯状況等の変更に伴い徴収免除の条件に該当することとなった場合は、変更手続きが必要となります。変更が生じた際は、速やかに必要書類を提出してください。年度内に限り、判定の変更を行います。
未申告等で税額の確認ができない場合は、副食費の免除が適用されないため、速やかに申告を行ってください。
年収360万円未満相当世帯のお子さま
1号認定…市区町村民税所得割額77,101円未満
2号認定…市区町村民税所得割額57,700円未満
(要保護世帯(ひとり親世帯もしくは障害者の方と同居されている世帯)の場合は77,101円未満)
第3子以降のお子さま (認定区分により第3子以降の数え方が異なります)
1号認定…小学校第3学年修了前の同一世帯のお子さまを数えて第3子
2号認定…小学校就学前の同一世帯かつ保育所等に通うお子さまを数えて第3子
公立保育所の給食食材の産地公表について
延長保育について
延長保育とは保育標準時間、または保育短時間で定められる時間を越えて、保育を利用することです。施設の開所時間の範囲内でご利用が可能です。 なお、延長した時間に応じて延長保育料が発生します。
保育施設によって、延長保育料の金額が異なりますので、詳しくは各保育施設へお尋ねください。
| 保育の必要量 | 延長保育利用時間 | 延長保育料 |
| 保育標準時間 | 18時30分から19時00分まで | 月額2,000円 |
| 保育短時間 | 16時30分から18時30分まで | 月額1,000円 |
| 18時30分から19時00分まで | 月額2,000円 |
支払い方法について
保育料・給食費の口座振替日について
保育料及び給食費については、下記の通りとなります。『桜井市』が徴収する保育料及び給食費の口座振替日は毎月25日(土日祝日の場合翌営業日)です。『施設』が徴収する場合については、直接各保育施設へご確認ください。
| 項目 | 公立保育所 | 私立保育所 |
認定 こども園 |
地域型 保育事業所 |
||
| 市 内 | 市 外 | 市 内 | 市 外 | |||
|
給 食 費 |
桜井市 | 施 設 | 施 設 | 施 設 | 施 設 | 施 設 |
| 保 育 料 | 桜井市 | 施 設 | 桜井市 | 桜井市 | 施 設 | 施 設 |
市内公立保育所の延長保育料について
市内公立保育所(第1保育所、第2保育所、第3保育所、第5保育所)の延長保育料については、利用月の翌月中旬頃に各公立保育所へ納付書を渡しますので、こどもの送迎時に保育所の先生より声掛けがありましたら、現金にてお支払いください。
なお、市内公立保育所以外の保育施設については、各保育施設が徴収しますので、直接各保育施設へご確認ください。
桜井市内の保育施設、他の詳細のページは下記のリンク
入所申込詳細のページは下記のリンク
お問い合わせ
桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 保育教育係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2223)
ファックス:0744-48-5175
メールフォームによるお問い合わせ
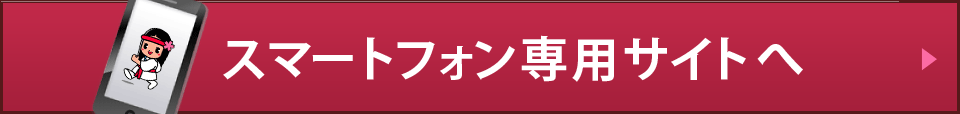














更新日:2024年06月11日