幼児教育無償化について
幼児教育無償化について
令和元年10月より幼児教育無償化が始まりました。このページでは主に桜井市に在住し幼稚園に通われているお子さまを対象として、幼児教育無償化の対象範囲、給付限度額、必要な申請、無償化の給付方法についてご案内します。
(リンク先:こども家庭庁ホームページ)も併せてご覧ください。
幼児教育無償化の対象者および給付限度額について
【公立幼稚園、私立幼稚園(新制度)に通園している方】
・幼稚園に通われている3歳児から5歳児の市で定められていた利用者負担額(保育料)が無償となります。
1、新制度の幼稚園とは子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園であり、市内では公立幼稚園と私立のさくら幼稚園、大三輪幼稚園が該当します。
2、保育料以外に園で徴収される諸費用は無償化の対象となりません。(入園料を含む)
(注意)さくら幼稚園は、令和6年度より認定こども園になりました。
【私立幼稚園(未移行)に通園している方】
・幼稚園に通われている3歳児から5歳児の保育料が月額2万5,700円までを限度として無償となります。
1、未移行の幼稚園とは子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園であり、市内では私立の育成幼稚園が該当します。
2、満3歳児は3歳になった日以降に幼稚園に正式に入園できる日から無償化の対象となります。
3、実際の保育料支払い金額が月額限度額を下回る場合は、実際の支払額を限度額とします。その場合、月額限度額との差額を他のサービス料に適用することはできません。(入園料を除く)
4、実際の保育料が月額限度額を上回る場合、月額限度との差額は自己負担となります。
5、保育料に含まれている給食費、送迎費などの特定費用は無償化の対象となりません。
【幼稚園に通園し、預かり保育を利用している方】
事前に保育の必要性の認定を受けた世帯を対象として、預かり保育利用料のうち 450円×利用日数(月額限度) までが給付されます。
1、その月の利用日数が25日を超えた場合、月額11,300円までが上限額となります。
2、満3歳児の場合は、保育の必要性とは別に市民税非課税世帯であることも条件となります。なお保育料と同様に3歳になった日以降に幼稚園に正式に入園できる日から対象となります。
3、満3歳児も同様に月額限度は 450円×利用日数 で算定しますが、月額上限は16,300円となります。
4、実際の預かり保育利用料支払い金額が限度額を下回る場合、実際の支払額を限度額とします。
5、預かり保育利用料に含まれるおやつ代や食事代は、無償化の対象になりません。
保育の必要性について
幼稚園の預かり保育を利用しており、預かり保育利用料を給付対象とする場合は「保育の必要性」の認定を事前に受ける必要があります。これが認定されなければ預かり保育利用料は自己負担となります。保育の必要性がある状態とは保護者が夫婦共働きなどの理由において、ご家庭で子どもを保育することのできない状態をいいます。申請時には添付書類(証明書等)の提出が必要になります。
| 保育の必要性が認められる理由 | 認定の有効期間 |
|---|---|
| ・就労(1か月に1人あたり64時間以上労働することを常態としている場合) | ・当該子どもの小学校就学まで(現況確認を年に1回行います) |
| ・疾病にかかり、若しくは負傷し、精神若しく身体に障害を有している場合 | ・当該子どもの小学校就学まで(現況確認を年に1回行います) |
| ・同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護または看護している場合 | ・当該子どもの小学校就学まで(現況確認を年に1回行います) |
| ・震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 | ・当該子どもの小学校就学まで(現況確認を年に1回行います) |
| ・妊娠中であるかまたは出産後間がない場合(出産前後2か月) | ・出産日から2か月を経過した日の月末まで |
| ・求職活動中(起業準備を含む)を継続的に行っている場合 | ・有効期間の開始日から90日を経過する日の月末まで(子どもの小学校就学までの方が短い場合はその期間) |
| ・就学している場合 | ・保護者の卒業予定日まで(子どもの小学校就学までの方が短い場合はその期間)(現況確認を年に1回行います) |
| ・その他 | ・市長が必要と認める期間 |
注意:保育の必要性の認定は父母だけでなく、同居している20歳以上65歳未満の方も対象として認定を行います。(世帯分離している人も含む)
申請手続きについて
【公立幼稚園、私立幼稚園(新制度)に通園している方】
・通園しているすべてのお子さまについて教育標準時間認定(1号認定)【教育認定】の申請が必要です。
・幼稚園の預かり保育を利用し、「保育の必要性」がある場合は施設等利用給付認定(2号認定)【保育認定】の申請が必要です。
1、新制度の幼稚園とは子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園であり、市内では公立幼稚園と私立のさくら幼稚園、大三輪幼稚園が該当します。
2、在園している方は入園時に1号認定を申請していただいてます。無償化にあたって再度申請は必要ありません。
3、施設等利用給付認定(2号認定)【保育認定】は事前に申請が必要です。認定の遡及適用はできませんのでご了承ください。なお申請時には、就労証明書などをご提出いただく必要があります。
4、保育認定が受けられない場合、預かり保育利用料は自己負担となります。
【私立幼稚園(未移行)に通園している方】
・施設等利用給付認定(1号認定)【教育認定】または、幼稚園の預かり保育を利用し「保育の必要性」がある場合は施設等利用給付認定(2号認定)【保育認定】の申請が必要です。
1、未移行の幼稚園とは子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園であり、市内では私立の育成幼稚園が該当します。
2、満3歳児の保育認定は施設等利用給付認定の3号認定となります。保育の必要性とは別に住民税非課税世帯であることが必要です。
3、無償化の対象とする場合は、必ず事前に申請してください。認定の遡及適用はできませんのでご了承ください。
4、施設等利用給付認定(2号認定)【保育認定】の申請時には、就労証明書などをご提出いただく必要があります。
5、保育認定が受けられない場合、預かり保育利用料は自己負担となります。
【年度途中から保育の必要性の要件に当てはまるようになった方】
年度途中に家庭の状況が変わり、保育の必要性の要件に当てはまる場合は認定開始月の前月の10日までに、必要書類をそろえて申請書を保育教育課の窓口にご提出ください。保育が必要な理由を証明する書類をご確認ください。
保育が必要な理由を証明する書類について (PDFファイル: 111.9KB)
1、例えば6月より保育認定を受ける場合、5月10日までに書類をそろえて変更申請していただく必要があります。
2、申請書および勤務証明書などの様式は保育教育課の窓口にご用意しております。期限がありますので、余裕を持って取りに来ていただきますようお願いします。なおご家庭の状況を確認させていただきますので、ご家庭の状況を説明できる方が取りに来てください。
3、預かり保育を給付対象とする場合は、保育認定を事前に行う必要があります。認定の遡及適用はできませんので、ご了承ください。
【来年度幼稚園に新入園される方】
来年度4月より幼稚園に新入園される場合、施設等利用給付認定申請書は令和8年1月中旬以降(一部を除く)に幼稚園より配布させていただきます。幼稚園の指示に従い、提出期限までに幼稚園にご提出をお願いします。保育が必要な理由を証明する書類は、下記より必要な様式を印刷し、使用ください。
【雇用されている方・記入例】就労証明書 (PDFファイル: 480.8KB)
【自営業の方・記入例】就労証明書 (PDFファイル: 481.1KB)
注意:自営業の方で必要書類が添付できない場合は民生・児童委員証明欄の入った下記の様式をご使用ください。
【民生・児童委員証明欄入り】就労証明書 (Excelファイル: 49.4KB)
【記入例】就学等(予定)証明書 (PDFファイル: 132.6KB)
【幼稚園に在園し、施設等利用給付(2号認定)【保育認定】を受けている方】
来年度の4月以降も【保育認定】を継続する場合、現況届出書をご提出いただき、【保育認定】を継続できるか審査させていただく必要があります。令和8年1月中旬以降に幼稚園を通じて現況届出書を配布させていただきますので、申請書に就労証明書等を添付いただき、提出期限までに幼稚園へご提出ください。
なお「保育を必要な理由を証明する書類」は、上記より必要な様式を印刷し、使用してください。
給付方法について
【公立幼稚園、私立幼稚園(新制度)に通園している方】
・通園しているすべての子どもの利用者負担額(保育料)が0円となることから、保育料を支払う必要がなくなります。
1、新制度の幼稚園とは子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園であり、市内では公立幼稚園と私立のさくら幼稚園、大三輪幼稚園が該当します。
2、園によって無償化の対象とならない諸費用の徴収があります。
(注意)さくら幼稚園は、令和6年度より認定こども園になりました。
【私立幼稚園(未移行)に通園している方】
・保育料は幼稚園より市に請求されることから、保育料を支払う必要がなくなります。
1、未移行の幼稚園とは子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園であり、市内では私立の育成幼稚園が該当します。
2、保育料が月額2万5,700円を超える場合、差額は自己負担分として幼稚園にお支払いください。
3、無償化の対象とならない諸費用は、今まで通り幼稚園にお支払いください。
【幼稚園の預かり保育を利用し、保育認定(2号認定)を受けた方】
・預かり保育の利用料は、一旦幼稚園にお支払いください。後日、請求書を作成いただき、その請求に基づいて保護者さまの口座に還付します。(償還払い)
1、預かり保育利用料のうち 450円×利用日数(月額限度) までが給付され、その月の利用日数が25日を超えた場合、月額11,300円までを上限として給付します。(満3歳児は月額16,300円)
2、請求書は毎月分作成してください。各幼稚園に取りまとめをお願いしていますので、作成については幼稚園の指示に従ってください。
3、公立幼稚園の預かり保育利用料は、月額限度を超えないことから保育認定を受けた方は預かり保育利用料が0円となります。公立幼稚園の預かり保育の利用だけであれば、請求書の作成は必要ありません。
【預かり保育利用料の請求書の書き方】
施設等利用費の請求書の書き方【私立幼稚園用】 (PDFファイル: 1.2MB)
1、請求者は認定通知書に記載された保護者氏名(認定保護者)を記入してください。
2、振込先の銀行口座について、ネット銀行は取り扱いができません。預金種目は普通または当座に限ります。
3、振込口座は認定保護者名義の口座に限られます。口座名義人が異なる場合は、請求ごとに委任状の提出が必要となります。
4、初回請求および振込口座を変更する場合に限り、振込口座の登録ミスを防止するため通帳の表紙裏面のコピーを提出してください。振込先が変わらない場合、「前年度に償還払いを受けた進級児」および「その進級児の弟・妹」は提出不要です。把握が困難であるため、卒園児の弟・妹は再度提出をお願いします。
5、請求額に間違いがないようご注意ください。
認可外保育施設等の利用について
・公立幼稚園や市外の一部の私立幼稚園では園での預かり保育のほかに市町村の確認を受けた認可外保育施設、病児保育所、一時預かり事業、ファミリーサポートセンターの預かりの利用が月額限度の範囲内で無償化の対象となります。【保育認定を事前に受けた方のみ対象】
1、認可外保育施設等の利用が対象となるのは、幼稚園の預かり保育の実施時間が平日8時間未満(教育時間を含む)または年間計画日数が200日未満の場合です。
2、市内の私立幼稚園に通園している場合、認可外保育施設等の利用は無償化の給付対象となりません。
3、送迎のみの利用は対象外となります。
4、幼稚園の預かり保育利用料と合わせて、月額11,300円まで(満3歳児は月額16,300円)が給付対象となります。【園での預かり保育は450円×利用日数で算定】
5、市外の公立幼稚園では認可外保育施設等の利用が対象とならない場合がありますので、ご注意ください。
桜井市内の保育施設、他の詳細のページは下記のリンク
入所申込詳細のページは下記のリンク
お問い合わせ
桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 保育教育係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2223)
ファックス:0744-48-5175
メールフォームによるお問い合わせ
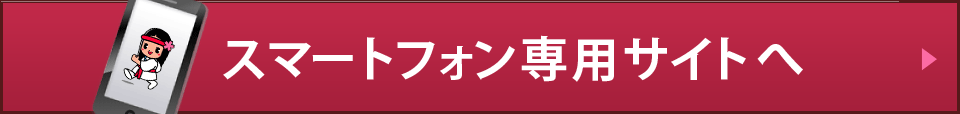














更新日:2025年01月06日